『標本室の午後』
七月の湿気が、古びた校舎の廊下に澱んでいる。
放課後の気配はとうに消え失せ、遠くで運動部の掛け声が微かに響くだけだ。
それがかえって、この特別教室――理科準備室の静寂を、耳鳴りがするほど際立たせていた。
西日が遮光カーテンの隙間から差し込み、埃の舞う空気を黄金色の帯となって切り裂いている。
その光の先、部屋の中央にある実験台の椅子に、彼女は座っていた。
名前を呼ぶ必要はない。
彼女はここに存在するだけで、その役割を全うしているのだから。
白い半袖のブラウス。紺色のプリーツスカート。首元には少し緩んだリボン。
世間が「女子高生」と呼ぶ記号のすべてを身に纏いながら、彼女は石像のように動かない。
いや、動けないのだ。私の視線が、彼女を縫い止めているから。
「……先生、まだですか」
沈黙に耐えかねたのか、彼女が微かに唇を動かした。
その声は震えていた。恐怖か、あるいは期待か。未熟な彼女自身にも判別がつかないのだろう。
「焦ってはいけないよ。観察には時間が必要なんだ」
私はガラス棚の前に立ち、背を向けたまま答える。
棚にはホルマリン漬けの生物たちが、永遠の眠りについている。
色褪せたカエルの腹、白濁した液に浮かぶ蛇の眼球。
彼女もまた、この部屋に足を踏み入れた瞬間から、彼らと同じ「標本」になったことに気づいているのだろうか。
私はゆっくりと振り返り、彼女に歩み寄る。
革靴が床を叩くコツ、コツ、という音が、彼女の心臓の鼓動と重なっていくのが手に取るようにわかる。
彼女は膝の上で固く拳を握りしめている。
爪が掌に食い込むほどに。その痛みだけが、今の彼女を現実に繋ぎ止める唯一の錨なのだろう。
実験台の前で足を止める。
彼女との距離、わずか三十センチ。
若さ特有の、甘く、少し酸味を帯びた汗の匂いが鼻腔をくすぐる。
制汗スプレーの人工的な柑橘の香りが、かえって彼女の生々しい体温を強調していた。
「髪を、上げてごらん」
私の命令は、低いが、拒絶を許さない響きを持っていたはずだ。
彼女は一瞬、肩を跳ねさせたが、やがて観念したようにゆっくりと手を挙げた。
細い指が、肩にかかる黒髪をかき上げる。
露わになったうなじ。
そこには、夏の暑さに滲んだ汗が、幾筋もの透明な川を作っていた。
後れ毛が肌に張り付き、白磁のような肌とのコントラストを描き出している。
美しい。
理性が崩壊するほどに、無防備で、無垢だ。
私は指先を伸ばし、その汗の一滴を拭うかのように、空中でなぞった。
触れてはいない。
だが、彼女の喉が小さく鳴り、肌が粟立つのをはっきりと見た。
物理的な接触など、この濃密な空間においては野暮というものだ。
視線で触れ、気配で犯す。
彼女は今、服を着ているにもかかわらず、精神的には丸裸にされているのだから。
「君は、美しいね」
「……やめて、ください」
「何を? 私はただ、見ているだけだよ」
彼女の拒絶は、懇願に似ていた。
逃げ出そうと思えば逃げ出せるはずだ。扉には鍵など掛かっていない。
だが、彼女は動かない。
私の瞳というレンズ越しに自分自身を見つめられ、その「被写体」としての価値を刷り込まれてしまっている。
教師と生徒。大人と子供。観察者と標本。
その圧倒的な高低差が生み出す重力に、彼女の魂は縛り付けられている。
ブラウスの背中が、汗で透け始めているのが見えた。
薄い布一枚の下にある、心臓の早鐘。華奢な背骨のライン。
そのすべてが、私の所有物であるかのような錯覚。いや、この閉ざされた理科準備室の中では、それは真実となる。
私は机の上にあった長い定規を手に取った。
ひやりとした金属の質感。
それを、彼女の二の腕にそっと当てる。
ビクリ、と彼女の体が跳ねる。
「体温が高いな。……三十七度、いや、もっとあるか」
定規の冷たさが、彼女の熱を奪っていく。
彼女は顔を伏せ、耳まで赤く染めながら、荒い息を繰り返している。
その姿は、網に掛かり、力尽きるのを待つ蝶のようだ。
羽ばたけば羽ばたくほど、鱗粉が剥がれ落ち、美しく損なわれていく。
窓の外で、ヒグラシが鳴き始めた。
カナカナカナ……という哀切な響きが、室内の重苦しい空気をさらに煮詰めていく。
夕日がより一層赤みを増し、教室全体が琥珀色の樹脂の中に沈んでいくようだった。
「……そろそろ、時間だ」
私がそう告げると、呪縛が解けたように、彼女は弾かれたように顔を上げた。
その瞳は潤み、焦点が定まっていない。
安堵と、そして奇妙な喪失感が入り混じった複雑な表情。
「帰りなさい。……気をつけて」
彼女は慌てて鞄を掴み、逃げるように扉へと向かう。
だが、ノブに手をかけた瞬間、彼女は一度だけ振り返った。
私を見るその瞳の奥には、恐怖だけではない、どこか熱っぽい光が宿っていた。
自分が「見られる」ことによって初めて存在を許された、そんな倒錯した悦びの種が、彼女の中に芽生えたのかもしれない。
バタン、と扉が閉まる。
再び訪れた静寂。
残されたのは、彼女が座っていた椅子の温もりと、甘酸っぱい残り香だけ。
私は実験台に手をつき、深く息を吸い込んだ。
その空気は、何よりも濃厚で、背徳的な味がした。
少女は去ったが、彼女の一部は、確かにこの部屋の標本棚に新たに加えられたのだ。
永遠に色褪せない、夏の日の記憶として。
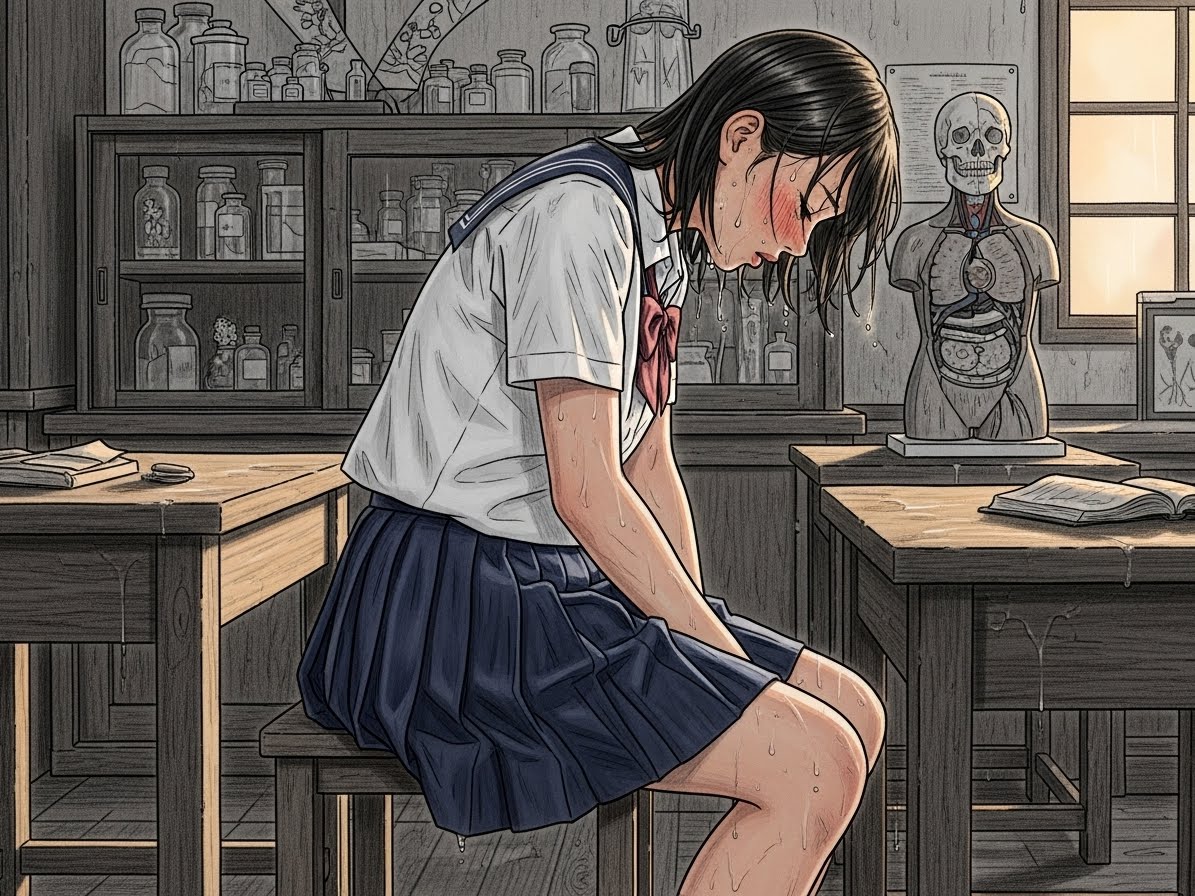


コメント